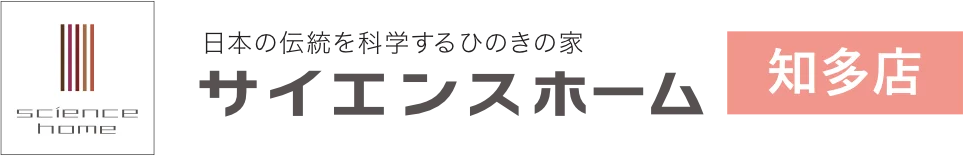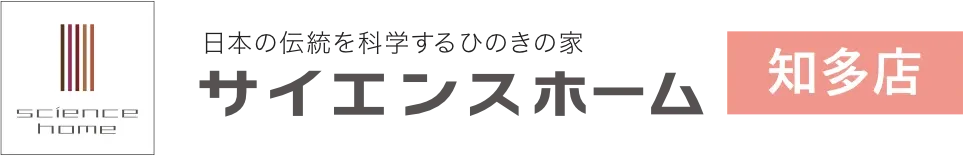注文住宅の家庭用発電で後悔しないための費用と導入判断のポイント
2025/11/03
注文住宅で家庭用発電の導入を検討している中で、不安や疑問を感じていませんか?夢の注文住宅だからこそ、太陽光発電などの最新設備に踏み切るべきか、費用やデメリットも気になるものです。設置コスト・メンテナンス・補助金の活用、そして発電効率や売電・電気代の節約など、多角的な視点から家庭用発電のリアルを分析します。本記事を読むことで、注文住宅に家庭用発電を取り入れる際に後悔しない判断ができ、長期的に満足できる住まいづくりへと一歩踏み出せます。
目次
注文住宅で後悔しない発電導入の秘訣

注文住宅で発電設備を選ぶ際の重要な判断基準
注文住宅で家庭用発電設備を選ぶ際には、「初期費用」「発電効率」「設置可能な屋根面積」「メンテナンスのしやすさ」「補助金や助成制度の有無」など、複数の観点から総合的に判断することが欠かせません。特に太陽光発電の場合、屋根の形状や方角が発電効率に大きな影響を与えるため、設計段階から十分な打ち合わせが必要です。
また、発電した電気を「自家消費」するか「売電」するかによっても、必要な設備や蓄電池の有無が変わります。電力会社との契約や制度変更にも注意が必要であり、長期的なランニングコストや将来のリスクも見据えておくべきです。実際に、設備の選定ミスで思ったほど電気代が削減できなかったという声も少なくありません。

注文住宅で家庭用発電を導入する決め手とは何か
家庭用発電の導入を決める最大のポイントは、「電気代の削減」と「災害時の備え」です。特に電気料金の高騰や停電リスクが高まる中、太陽光発電と蓄電池の組み合わせは大きな安心材料となります。一方で、初期費用や設置後のメンテナンス費用も無視できません。
たとえば、補助金の活用や売電収入を見込める場合は、導入メリットが大きくなります。逆に、屋根の面積が狭い・日当たりが悪い・将来的な制度変更のリスクを重視する場合は、慎重な判断が求められます。家族構成やライフスタイルによっても最適な選択肢は異なるため、事前のシミュレーションが重要です。

注文住宅の発電導入で後悔しないための実践ポイント
後悔しないためには、設置費用とランニングコスト(メンテナンス費用など)を明確に把握し、期待できる発電量や電気代削減効果を具体的に試算することが大切です。導入前には、複数社の見積もりを比較し、補助金や優遇制度の最新情報も調べておきましょう。
また、設置後のトラブル(例:思ったより発電しない、メンテナンスが高額)を避けるため、保証内容やアフターサービスの確認も欠かせません。実際に導入した方の体験談を参考にすることで、現実的なメリット・デメリットが見えてきます。初心者は専門家のアドバイスを活用し、経験者は将来の売電制度変更にも備えたプランを検討するとよいでしょう。

注文住宅で太陽光発電を検討する際の注意点
注文住宅で太陽光発電を検討する際は、屋根の形状・方角・面積が発電効率や設置費用に直結します。特に、屋根の勾配や周囲の遮蔽物による影響は見落とされがちで、これが原因で十分な発電量が得られないケースもあります。
さらに、将来的なメンテナンスや部品交換のコスト、売電価格の低下や制度変更のリスクも考慮する必要があります。「太陽光発電はやめたほうがいい理由は何か」といった疑問を持つ方も多いですが、実際には家庭の状況や設置環境によるため、事前の現地調査とシミュレーションが不可欠です。

注文住宅に家庭用発電が適しているケースを知る
家庭用発電が特に適しているのは、日当たりの良い屋根面積が十分に確保できる住宅や、電気の自家消費率が高いご家庭です。また、災害時の備えとして電力の自給自足を重視する場合にも有効です。共働き世帯や在宅ワークが多いなど、昼間の電力使用量が多い家庭は導入効果が大きい傾向にあります。
一方で、屋根面積が限られている、日照条件が悪い、初期費用の回収が難しいといった場合は慎重な検討が必要です。蓄電池を組み合わせることで災害時の安心感が高まりますが、追加費用も発生します。自分の家庭に合った最適な発電設備を見極めるため、専門家への相談や実際のシミュレーションを活用しましょう。
太陽光発電が注文住宅に必要か再考しよう

注文住宅に太陽光発電が本当に必要か見極める方法
注文住宅で太陽光発電システムの導入を検討する際は、家庭やライフスタイルに本当に必要かどうかを冷静に見極めることが重要です。まず、設置費用や初期費用といったコスト面、太陽光発電の発電効率、地域の日照条件などを具体的に確認しましょう。例えば、日照時間が長い地域では発電量が多くなりやすいですが、逆に曇りやすいエリアでは期待ほどの効果が得られない場合もあります。
また、家族の電気使用量や今後のライフスタイルの変化も考慮に入れることが大切です。売電収入や電気代削減を重視する場合は、蓄電池の併用や自家消費の比率も検討ポイントとなります。導入の判断には、補助金制度やメンテナンス費用など、長期的な総額でシミュレーションを行うことが後悔しないためのコツです。
実際に設置した方の体験談では、「設置後に思ったよりも電気代が下がらなかった」「メンテナンスの手間や費用が予想外だった」といった声が見受けられます。導入前に複数の業者に見積もりをとり、メリット・デメリットを整理しておくことで、納得感のある判断ができるでしょう。

注文住宅で太陽光発電いらないという意見の背景
注文住宅で「太陽光発電はいらない」という意見も根強く、その背景にはいくつかの理由があります。第一に、設置費用が高額であることや、初期投資の回収に時間がかかる点が挙げられます。特に、太陽光発電の価格や設置費用が家計に大きな負担となる場合は、導入をためらう方が多い傾向です。
また、太陽光パネルや蓄電池のメンテナンス、設備の耐用年数や交換コストも無視できません。さらに、屋根の形状や方角が発電効率に大きく影響するため、すべての注文住宅で最大限の効果が得られるわけではないという現実もあります。加えて、売電価格の下落や制度変更による収入減少も懸念材料です。
実際に「設置後に思ったほどのメリットがなかった」「売電収入が予想より少なかった」といった後悔の声も、ネット上や口コミで見受けられます。こうした意見を踏まえ、自分たちの住まいに本当に必要かどうかを、冷静に検討することがポイントです。

太陽光発電義務化に備えた注文住宅の選択肢
近年、一部の自治体や都市部では新築住宅への太陽光発電設置が義務化される動きが強まっています。今後注文住宅を建てる際は、こうした制度や法規制を事前に確認し、将来的な義務化に備えたプランニングが重要です。特に東京などでは2025年以降の義務化が話題となっており、設計段階から屋根の形状や設置スペースを確保しておく必要があります。
義務化に対応するための選択肢としては、発電効率の高い太陽光パネルの採用や、蓄電池との組み合わせによる自家消費の強化が挙げられます。また、補助金や優遇制度の活用も費用負担を軽減する有効な手段です。自治体ごとに条件や制度が異なるため、最新情報を必ず確認しましょう。
今後の制度変更に柔軟に対応できるよう、設計士や施工会社と十分に相談し、将来的なリフォームや設備拡張も視野に入れておくと安心です。義務化を見据えたスマートな家づくりが、長期的な満足につながります。

太陽光発電を新築で迷う人が押さえたいポイント
新築注文住宅で太陽光発電の導入を迷う方は、まず設置費用と予想される光熱費削減効果を具体的に比較することが大切です。太陽光発電システムの価格や設置費用は戸建ての規模や屋根の形状によって異なります。平均的な設置費用や発電量の目安を把握し、将来的な電気代の削減額とバランスを見極めましょう。
また、売電だけでなく蓄電池を活用した自家消費の割合を高めることで、災害時の備えや電気料金の変動リスクにも対応できます。補助金や自治体の支援策を活用することで初期負担を軽減できる場合もあるため、最新の情報収集が欠かせません。メンテナンス頻度や耐用年数、保証内容も導入前にしっかり確認しましょう。
実際の導入事例では、「補助金を活用して設置費用を抑えられた」「停電時に蓄電池が役立った」という声もあります。迷った場合は、複数の専門業者に相談しシミュレーションを依頼することで、納得のいく判断がしやすくなります。

注文住宅で太陽光発電の必要性を再確認する理由
注文住宅で太陽光発電の必要性を再確認する理由は、単なる省エネだけでなく、長期的な家計の安定や災害時の安心感にあります。電気代の削減や売電収入に加え、再生可能エネルギーの自家消費によるエネルギー自立も大きなメリットです。特に近年の電力会社料金の変動や停電リスクを考えると、家庭用発電設備の価値は高まっています。
ただし、初期費用やメンテナンス、将来の設備更新など、長期的な視点でコストとメリットのバランスを見極めることが不可欠です。補助金や優遇制度の活用、発電効率の高い設備の選定など、具体的な対策を講じることで、後悔のない選択につながります。
実際に太陽光発電を導入した家庭からは、「電気代が大幅に削減できた」「災害時にも生活が止まらなかった」といった満足の声が寄せられています。自分たちのライフスタイルや将来設計に合わせて、必要性を見直してみることが大切です。
家庭用発電の価格とメリット徹底解説

注文住宅で家庭用発電を導入する価格相場とは
注文住宅で家庭用発電、特に太陽光発電の導入を検討する際、最も気になるのは設置費用の相場です。一般的な家庭用太陽光発電システムの設置費用は、容量や設備内容、屋根の形状によって大きく異なりますが、3kWから5kW程度のシステムで約80万円から200万円が目安となります。
この価格には太陽光パネル、パワーコンディショナー、架台、工事費などが含まれます。最近では蓄電池を同時に導入するケースも増えており、蓄電池の追加でさらに100万円前後の費用がかかることもあります。地域によっては自治体の補助金や国の制度を活用できる場合があり、実質的な負担額が軽減されることもあります。
また、注文住宅の場合は建物設計段階から発電設備を組み込めるため、後付けよりも施工がスムーズで、コスト面で有利になる場合もあります。その一方で、「太陽光発電 いらない」「太陽光発電やめたほうがいい」という声もあるため、価格だけでなく導入後のメリット・デメリットも十分に比較検討することが大切です。

太陽光発電設置費用や注文住宅のメリットを解説
太陽光発電の設置費用は、太陽光パネルの性能や設置面積、屋根の向き・形状、工事の難易度などにより変動します。注文住宅なら、最初から太陽光発電を前提に屋根の形状や方角を最適化できるため、発電効率を上げつつ工事コストも抑えやすいのが大きな特徴です。
また、注文住宅では「新築 義務化」や「太陽光発電 設置費用 戸建て」のような最新の法制度や補助金制度を調べて活用しやすいメリットがあります。設計時に専門家と相談しながら、住宅の断熱性や耐震性と合わせて最適な発電設備を導入できる点も見逃せません。
一方で、設置費用のみならず、将来的なメンテナンスコストや設備の寿命、売電価格の変動リスクも考慮する必要があります。初期費用を抑えるために「0円ソーラー」などの選択肢もありますが、契約内容や将来の制約をよく確認することが後悔しないポイントです。

注文住宅の太陽光発電で得られるメリットと注意点
注文住宅に太陽光発電を導入することで、電気代の削減や売電収入の獲得、災害時の非常用電源の確保といったメリットがあります。特に近年は電気料金の上昇が続いており、自家消費による光熱費の節約効果がより実感しやすくなっています。
一方、太陽光発電にはデメリットや注意点も存在します。例えば、設置後のメンテナンスやパワーコンディショナーの交換費用、天候や地域差による発電量の変動、売電単価の下落リスクなどが挙げられます。また、「太陽光発電やめたほうがいい理由」や「注文住宅 太陽光発電 いらない」といった意見も、こうしたデメリットを背景にしています。
導入を検討する際は、将来のライフスタイルや家族構成の変化も見据え、初期費用だけでなく長期的な維持コストやリスクも踏まえて判断しましょう。実際に導入した方の口コミや失敗談・成功例も参考になります。

家庭用発電システムの価格と費用対効果を比較
家庭用発電システムには、太陽光発電だけでなく、蓄電池やエネファーム(家庭用燃料電池)などの選択肢もあります。価格は太陽光発電が3kWで約100万円前後、蓄電池は容量や性能によって100万~200万円程度、エネファームは100万~150万円が一般的な目安です。
費用対効果を比較する際は、初期費用だけでなく、年間の電気代削減額や売電収入、メンテナンス費用、設備の寿命(15~20年が目安)などを総合的に考える必要があります。特に「太陽光発電 家庭用 価格」や「太陽光発電 設置費用 平均」といった情報を参考に、シミュレーションを行うと効果が具体的に見えてきます。
注意点としては、売電単価の減少や制度変更による収支の変動リスク、設備の故障や交換時の出費などがあります。将来的な電気自動車との連携や、再生可能エネルギー活用の観点からも、長期的な視点で費用対効果を検討しましょう。

注文住宅に最適な発電設備の価格帯をチェック
注文住宅に最適な発電設備は、家族構成やライフスタイル、希望する発電量によって異なります。一般的には、4人家族の標準的な住宅で4kWから5kW程度の太陽光発電システムが選ばれることが多く、設置費用は約120万~180万円が目安です。
さらに、災害時の備えや電気の自家消費を重視する場合は、蓄電池の導入も検討されます。蓄電池は容量や機能によって価格に幅がありますが、100万~150万円程度が一般的です。注文住宅では設計段階から発電設備を組み込めるため、屋根形状や設置スペースの最適化が容易で、発電効率を最大限に引き出しやすい利点があります。
導入前には、各メーカーの製品仕様や保証内容、補助金の有無も含めて複数社から見積もりを取得し、総合的に比較検討しましょう。将来の電力需要や家族の成長も見据えた設備選びが、後悔しないポイントとなります。
設置で迷うなら家庭用発電の実例を参考に

注文住宅で発電設置に迷った実例と解決策
注文住宅の計画段階で「太陽光発電を設置すべきか迷った」という声は非常に多く聞かれます。理由としては、初期費用や設置場所、日当たりなどの条件が家庭ごとに異なるため、判断が難しいことが挙げられます。特に、屋根の形状や方角、地域の気候によって発電効率が左右されるため、慎重な検討が必要です。
例えば、南向きの大きな屋根を持つ住宅では発電効率が高くなりやすいですが、北向きや影の多い立地では十分な効果が得られないこともあります。このようなケースでは、専門家に発電シミュレーションを依頼し、年間でどれだけ発電できるか、電気代削減や売電収入の見込みを具体的に算出することが重要です。
解決策としては、設置前に複数の業者から見積もりや発電シミュレーションを取り、設置費用・設置条件・補助金制度などを比較検討することが挙げられます。注文住宅ならではの柔軟な設計を活かし、将来的なメンテナンスや蓄電池の追加も視野に入れて総合的に判断することが、後悔しないポイントです。

家庭用発電を導入した注文住宅の体験談を紹介
実際に家庭用発電を導入した注文住宅のオーナーからは、「電気代が大幅に削減できた」「災害時も安心して生活できた」といった前向きな声が多く聞かれます。特に、蓄電池を併設したケースでは、停電時にも家電が使えるメリットを実感したという体験談が目立ちます。
一方で、初期費用の高さや、メンテナンスの手間に戸惑ったという声も存在します。例えば、太陽光パネルの定期的な点検や洗浄が必要であること、パワーコンディショナーなどの設備交換が10~15年ごとに発生することを想定していなかったという例も見受けられます。
体験者の共通点として、導入前に補助金や設置費用、維持費用をしっかり調べていた人ほど満足度が高い傾向があります。具体的なシミュレーションや専門家からのアドバイスを受けて判断したことが、成功の秘訣といえるでしょう。

発電の設置場所や条件を実例でイメージしよう
発電設備の設置場所は、屋根の向きや傾斜、周辺の建物や樹木による影響を考慮して決める必要があります。一般的に、南向き・30度前後の傾斜を持つ屋根が最も効率的ですが、注文住宅では屋根形状や外観デザインにもこだわる方が多いため、設計段階から発電システムを組み込むことが大切です。
例えば、屋根スペースが限られている場合は、発電容量が小さくなりがちですが、最新の高効率パネルを選んだり、カーポート上に設置する方法も検討できます。また、積雪地域や風の強い地域では、耐久性やメンテナンス性も重視しなければなりません。
設置条件を満たすためには、現地調査や設計士との綿密な打ち合わせが不可欠です。実際の設置事例を参考に、どのような制約があるか、どんな工夫で発電効率を高めているかを知ることで、理想に近い発電プランを実現できます。

注文住宅の家庭用発電で成功した事例の特徴
注文住宅で家庭用発電が成功した事例にはいくつか共通点があります。まず、設計段階から太陽光発電の導入を前提にプランニングを進めていること、そして設置費用や補助金制度を最大限に活用している点が挙げられます。
また、発電量のシミュレーションを事前に行い、将来の電気代削減効果や売電収入を具体的に試算していることも特徴です。さらに、蓄電池を併設することで自家消費を増やし、非常時の備えにもなっているケースが多く見られます。
成功事例の多くは、設備のメンテナンス計画も含めて長期的な視点で導入判断をしており、予期せぬトラブルや追加費用を最小限に抑えています。専門業者との連携や、最新の発電技術・制度情報を積極的に取り入れる姿勢も、満足度の高い住宅づくりにつながっています。

太陽光発電をやめたほうがいい実例から学ぶ
太陽光発電の導入を見送った、あるいは導入後に後悔したという実例も少なくありません。主な理由は、設置費用に対して期待したほどの電気代削減や売電収入が得られなかったこと、または日当たりや屋根の形が発電に適していなかったことが挙げられます。
特に、「0円ソーラー」や初期費用無料を謳うプランで契約したものの、長期的なリース費用やメンテナンスコストが想定以上にかかり、経済的なメリットを感じられなかったという声もあります。また、定期的なメンテナンスや設備交換が発生することを十分に理解していなかったため、予期せぬ出費に悩まされるケースも見受けられます。
これらの実例から学べるのは、設置前に本当に必要かどうか、設置条件や費用対効果を十分にシミュレーションし、納得した上で判断することの重要性です。安易な導入は避け、長期的な視点で検討することが後悔しないためのポイントです。
補助金や制度を活用した賢い選択とは

注文住宅で家庭用発電の補助金を上手に活用する方法
注文住宅に家庭用発電を導入する際、補助金を最大限に活用することが費用負担を抑える鍵となります。特に太陽光発電や蓄電池を設置する場合、国や自治体による補助制度が多く用意されているため、最新の情報をこまめにチェックすることが重要です。補助金の対象となる設備や条件は地域ごとに異なるため、事前に公式な案内や専門家への相談をおすすめします。
補助金申請の流れは、注文住宅の設計段階で発電設備の導入を検討し、見積もりや必要書類を揃えたうえで申請するのが一般的です。例えば、蓄電池と太陽光発電を同時に設置すると追加の助成が受けられるケースもあります。失敗しないためには、申請期限や必要書類、工事着工前後の手続きなど、細かな条件を確認しておくことが大切です。

補助金制度を使った注文住宅での発電導入ポイント
補助金制度を利用して注文住宅に家庭用発電を導入する際のポイントは、まず対象となる設備や条件を正確に把握することです。太陽光発電や蓄電池の設置費用の一部が補助される場合、制度ごとに補助金額や申請タイミングが異なります。最新の公的情報をチェックし、設計・契約時に補助対象かどうかを確認しましょう。
また、補助金は予算枠が限られている場合が多く、先着順や抽選となることもあります。後悔しないためには、早めの情報収集と申請準備が不可欠です。例えば、設計士や住宅会社に相談し、補助金を活用した最適な発電設備の選定や設置計画を立てることで、効率的な導入が実現できます。

注文住宅の太陽光発電で利用可能な支援制度とは
注文住宅で太陽光発電を導入する場合、国や自治体が提供する多様な支援制度を活用できます。代表的なものとして、太陽光発電システムや蓄電池の設置に対する補助金、再生可能エネルギー普及のための助成金などが挙げられます。これらの支援制度は、設置費用の負担軽減や長期的な電気代削減に寄与するため、積極的な活用が推奨されます。
具体的な支援例としては、国の補助金はもちろん、自治体独自の助成金や優遇制度もあります。たとえば、一定の発電効率や蓄電池容量を満たす場合、追加の補助が受けられるケースもあるため、設計段階から条件を確認しておくことが重要です。各制度の詳細は自治体や専門機関の公式サイトで確認し、必要な手続きを漏れなく行うようにしましょう。

発電設備導入で補助金をもらうための注意点
発電設備導入時に補助金を受け取るためには、いくつかの注意点があります。まず、申請時期や必要書類、事前申請が求められるかどうかを必ず確認しましょう。補助金によっては、着工前の申請が必須となる場合が多いため、工事スケジュールと合わせて計画的に進めることが大切です。
また、設備や工事内容が補助金の条件を満たしていないと、申請が却下されることもあります。例えば、補助対象となる太陽光パネルや蓄電池の性能基準を満たしているか、施工業者が登録事業者かどうかも重要なチェックポイントです。実際に「手続きの不備で補助金が受け取れなかった」という声もあるため、事前確認と専門家への相談が失敗回避のカギとなります。
発電効率や蓄電池導入の適切な判断軸

注文住宅で発電効率を高めるための基礎知識
注文住宅に家庭用発電を導入する際、発電効率を高めるには太陽光発電の特性や設置条件を理解することが重要です。発電効率とは、太陽光パネルが受けた太陽エネルギーをどれだけ電気に変換できるかを示す指標で、パネルの種類や設置角度、方位、屋根形状、周囲の影の有無などが大きく影響します。
例えば、南向きで傾斜角度が適切な屋根に設置すれば、より多くの発電が可能です。しかし、周囲に高い建物や樹木がある場合は影になりやすく、発電量が低下するリスクがあります。設計段階で日射シミュレーションを行い、最適な設置場所を検討することが後悔しないポイントです。
また、地域ごとの日照条件や気象状況も発電効率に影響します。注文住宅ならではの自由度を活かし、ライフスタイルや将来の電力需要も見据えて、効率的な発電計画を立てましょう。

家庭用発電に蓄電池が必要か判断するポイント
注文住宅で太陽光発電を導入する際、蓄電池を併設するかどうかは多くの方が悩むポイントです。蓄電池は昼間発電した電気をためて、夜間や停電時に活用できるため、電気の自家消費率を高めたり、災害時の備えになるメリットがあります。
一方で、蓄電池は初期費用が高額で、設置スペースの確保やメンテナンスが必要です。電気代の削減効果や売電単価の下落、今後の制度変更などを考慮し、ご家庭の電力使用状況や将来的な電動車導入の有無も踏まえて判断しましょう。
蓄電池の導入を検討する場合は、補助金制度やメーカー保証、寿命(一般的に10年程度)も事前に確認し、長期的なコストと利便性のバランスを見極めることが大切です。

注文住宅で発電効率を意識した設備選びの重要性
発電効率を最大限に引き出すためには、太陽光発電システムだけでなく、パワーコンディショナーや蓄電池などの周辺設備の選定も重要です。最新の高効率パネルや高変換効率のパワーコンディショナーを選ぶことで、同じ面積でもより多くの発電が見込めます。
また、設計段階から屋根の形状や強度、配線経路、将来的な拡張性も考慮しましょう。例えば、屋根に十分な強度がない場合は補強工事が必要となり、追加費用が発生することもあります。設置後のメンテナンス性や保証内容、故障時の対応も比較検討することが後悔を防ぐポイントです。
家庭ごとの電力使用パターンや生活スタイルに合わせて設備を選ぶことで、無駄なく効率的な発電・消費が実現し、長期的な家計の助けになります。

蓄電池導入で注文住宅の電気活用をさらに向上
蓄電池を導入することで、昼間に発電した電気を夜間や停電時にも利用できるため、電気の自家消費率が大きく向上します。特に近年は売電価格が下落傾向にあるため、発電した電気を自宅で使い切る「自家消費型」へのシフトが進んでいます。
例えば、共働き世帯や日中不在が多い家庭では、発電した電気をそのまま売電するだけでは十分なメリットを得られないケースがあります。蓄電池があれば、夜間や電気代の高い時間帯にためた電気を使うことで、電気代削減効果が高まります。
ただし、蓄電池の設置には初期費用やメンテナンスコストもかかるため、費用対効果やライフスタイルとの相性をよく検討し、補助金制度や製品保証も活用しながら導入を進めることが推奨されます。

発電効率とコストのバランスを考える注文住宅
注文住宅で家庭用発電を導入する際は、発電効率と初期費用・ランニングコストのバランスを重視することが大切です。高効率な設備は発電量が増える一方、設置費用も高くなる傾向があり、予算オーバーに注意が必要です。
発電設備の導入には、設置費用やメンテナンス費用、将来的な設備更新費用も見込んでおく必要があります。自治体の補助金や優遇制度を活用することで、初期負担を軽減できる場合もあるため、事前に情報収集を行いましょう。
長期的な電気代削減や災害時の備え、環境貢献など、費用以外のメリットも考慮し、家族構成やライフスタイルに合った最適な発電システムを選定することが、後悔しない注文住宅づくりへの近道です。